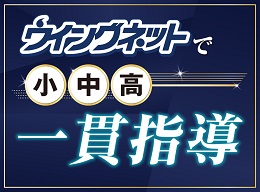全国玉井式研修セミナー in 東京 2045年に向けて─ 日本型教育の3つの課題から見える 真のグローバル教育への道 〜玉井式が提言する5つのMUST〜
9月10 日(日)東京・神保町の小学館本社の講堂において、(株)タマイ インベストメント エデュケーションズ(玉井満代代表、東京都新宿区)主催の「全国玉井式研修セミナー in 東京」が開催された。
玉井代表の講演をはじめ、玉井式教材を活用している塾・学校の表彰式、成功事例発表、分科会などが6時間にわたって行われた。ここでは玉井代表の講演の要旨を主にお伝えする。
未来を見据え、教育的課題を解決する教育を
1時間20分にわたって行われた玉井満代氏の講演のテーマは「2045年に向けて─日本型教育の3つの課題から見える真のグローバル教育への道〜玉井式が提言する5つのMUST〜」。
冒頭、変化の激しい現代社会においては、未来がどのような社会になっているかをある程度予想した上で子どもたちの教育を考える必要があると玉井氏は述べる。
1995年に第三次産業革命(パソコン・インターネット)が起き、2030年には第四次産業革命(汎用AI・全脳アーキテクチャ)が起こるであろうと予測される中、日本の未来に向けての教育には「AIによる仕事量と質の変化への対応とAIの開発力の強化」「人口激減の高齢化社会が進む日本とインド・中国などの人口・経済大国の教育推進化と競争力」「低すぎる自己肯定感」──という3つの大きな課題があるという。未来を見据えた教育を行うと同時に、これらの教育のゆがみも修正していく必要があると玉井氏は語る。
そしてそのために、現代の子育て世代が実現可能な「5つのMUST」を提案する。それは(1)睡眠時間を確保する(2)イメージング力を伸ばす(3)空間認識力を高める(4)常に世界を認識する(5)自己効力感を育む──の5つだ。
豊かな「イメージング力」を育む玉井式教材
当然のことではあるが、子どもにとって充分な睡眠をとることはとても重要だ。4〜6歳は10〜13時間、7〜12歳は9〜11時間の睡眠時間が必要とされ、睡眠不足が続くと、意欲減退、疲れやすい、集中力低下などに陥り、大人になってからも心身への影響は大きいというから、注意が必要だ。
大学入試改革が実施されると、各大学における個別選抜では、小論文、プレゼンテーション、集団討論などが行われる予定だが、「政府がなぜこちらに梶を切ったかというと、世界ではプレゼン力が弱いと仕事にならないからです」と玉井氏は述べる。
「今後は自分の専門分野において、自分がプレゼンをして伝える力を養っていかなければ世界で通用しません。そこまで落とし込んで教育を考えなければいけないことを、ぜひお母さんたちにお伝えください」。
例えば小学5年生で、300の英単語を教えることになったとして、その単語のテストをすれば点数はとれるだろう。「しかし目的は何かといえば、英語を使って自分を表現することです。大人が覚えさせようとするのではなく、たくさんの言葉を聞くことによって、子どもは単語を覚えていきます」。
日本語でも英語でも、言葉というツールをクリエイトして使うためには、言葉を使う思考力が必要だという。それを玉井式では「イメージング力」と呼び、全ての玉井式の教材には「イメージング」というテーマを与えているという。
「書く力」については、読んでいれば書けるようになるという。逆に言うと、多読しなければ書くことは難しい。「多読は人が書いて表現したものをインプットしますから、わざわざ書き方を習わなくても、やがて年齢に応じて書いて表現できるようになります」。
良質の言葉と音を使い、問題集と映像から成るICT教材
玉井式教材は『玉井式国語的算数教室』をはじめ『玉井式図形の極』『玉井式Eeそろばん』『玉井式国語的理科教室』があるが、どれも問題集と映像で構成されている。子どもが集中して観ることを念頭に入れ、良い言葉、良い音を使い、自ら次を読みたくなっていく工夫を凝らしているという。「『玉井式国語的算数教室』なので、問題集には算数力と思考力を育む問題が掲載されています」。
共働きの家庭が増え、親子で語らう時間が1日に2時間しかない中、思わず親子で話がはずむような教材でもあるという。
「かけ算を学習しているからといって、かけ算の文章題が出ているわけではありません。割り算や引き算など様々なものを混ぜて問題を作成しています。早く答えを出そうとするのではなく、じっくり考える問題になっているのが大きな特長です」。
『玉井式図形の極』は進級式(10級〜1級)になっていて、図形を極める7分野(平面図形、立体図形、展開図、角度、垂直と平行、比、動く図形)で構成されている。各分野を級ごとに繰り返し学習していくスパイラル方式で、子どもたちは楽しみながら空間認識力を高めることができるという。
「自己効力感」とは、簡単に言うと「自分が頑張れば変えていける」と思えること。「まずは自己効力感にフォーカスすべきだと思います。『どうせできない』ではなく『できる』というモチベーションを子どもに持たせます。1つでも2つでも、まずはやったことを肯定してあげて、小さな成功体験を積み重ねることによって『ずっとできる』という認識が持てるようにしてあげてください」。
講演の最後に、玉井氏はこう語った。「玉井式は〝学力と教養の土台づくり〟と位置づけ、〝段階を計算された算数の問題〟と〝思いやりを育む物語〟を取り入れております。
私とともに、この先も末永く一緒に考えながら進んでくださったら、こんなに嬉しいことはありません」。