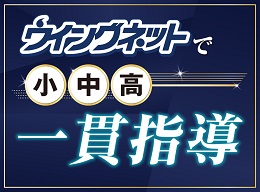AJC(全国学習塾協同組合)森貞孝理事長の最新教育情報 第15回
教育は宗教であり、科学であり、芸術である
11月は受験生にとって入試への最後の追い込みに入る期間だろう。東京を例にとれば2月1日に私立中学入試、10日に私立高校入試、22日から都立高校入試がある。2月1日まで余すところ13週を切るところまできた。
11月は秋も深まり、紅葉の季節。
秋の夜長は、気温も下がって、勉強にも力が入る。この時期に勉強に集中できた生徒は、目標を持ったり、勉強内容に興味を持ったりしているケースが多い。
あの先生から褒められたというキッカケで勉強に夢中に取り組んだ生徒がいる。小中学生にとって教師は絶対の存在になることも多い。また逆になったケースもよく聞く。それほど生徒にとって教師の存在は、学校の教師か塾の講師かは別として大きな影響を与えることが多い。
今いろいろなスポーツでパワハラが大きな話題を呼んでいる。アメリカンフットボールから始まって、女子の体操競技まで多くの生徒たちから今まで口に出せなかった様々なパワハラの状況がほとばしり始めた。
全国大会で優勝を争うようなクラブ活動は他の学校と同じ程度の練習量や指導法でそこまで上り詰めることはなかなかできない。あと一歩体力をつけ、あと一歩練習量を増やし、一丸となって目標めがけて努力していく先に栄冠がほほ笑んでくるのだ。
暴力はいけない。パワハラも生徒にとっては大きなプレッシャーになってのしかかってくる。その紙一重のところで頑張っていくクラブ活動も多いのだ。
学習塾の講師にとっても他人事ではない。少しでも学力を伸ばそう、目標校へ合格させようという講師の叱咤激励が生徒にどう受け止められているのか。生ぬるい指導で結果を出せない塾は淘汰されていく。暴力はいけないが、それに近い発言を生徒に対してしていることはないか。勉強に集中させるのではなくて勉強嫌いになるような指導や押し付けをしていないか。
私はかって「教育は宗教なり」「教育は科学なり 教育は芸術なり」という色紙を尊敬する先生からいただいた。
「教育は宗教なり」とはその先生の授業はみんな夢中になって聞きたがる。その先生の時間が待ち遠しい気持ちになる。そのように生徒の心を惹きつける指導をしようということだ。
「教育は科学なり」とはいくら生徒の心を惹きつけるような指導をしようとも少しでも間違っていたり、いい加減にごまかすような話は絶対にしない。
そして最後の「教育は芸術なり」とは授業時間の中で、徐々に生徒の心をつかんで、全員が理解し、大きな満足感を抱く。そういった大きなストーリーや芸術作品のような授業の構成を考えて指導しなさいという意味だ。
子どもたちの成長の過程で、あの先生のおかげで、あのひと言でこの子の人生が変わりましたと感謝されることは教師冥利に尽きる。全国の数百万の生徒たちの生涯に大きな影響力を与える塾の先生方がいることを、私は誇りに思っている。